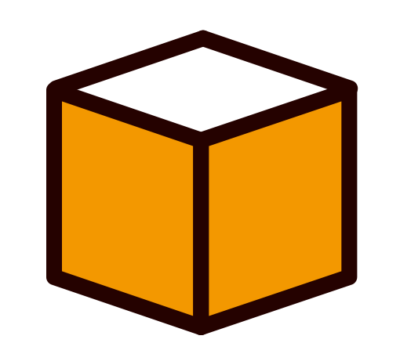想像力を鍛える本、アンデルセンの『絵のない絵本』で妄想してみる
想像力を鍛えたいなら、イメージトレーニングにおすすめの『絵のない絵本』
アンデルセンの絵のない絵本
童話作家アンデルセンによる、美しすぎる童話集『絵のない絵本』(Billedbog uden Billeder/Hans Christian Andersen)。『絵のない絵本』は、屋根裏部屋で暮らす絵描きの青年が、孤独な夜に月が語ってくれた話を書きつけたという設定の連作で、三十三夜のショートストーリーで構成されている。『絵のない絵本』は、一夜ごと、一話読むごとに想像力が刺激されて、情景や絵が頭の中に浮かびあがってきて、時に映画を観ているような気分になる。
朗読や演劇など、表現者が表現をするために「まず頭の中に映像を浮かべる」というトレーニングがある。自分がイメージできないものは、表現することはできない。歌えないし、朗読できないし、演奏もできない。合奏コンクールで歴代上位に入っている学校では、「課題曲から映像をイメージさせる」という指導を取り入れているそうだ。まずは映像をきちんと浮かべること、それが大切になってくる。
『絵のない絵本』で映像を思い浮かべていると、なぜアンデルセンがこの本に『絵のない絵本』というタイトルをつけたのかがわかる気がしてくる。全てのお話が、絵本みたい…というか、映像になって浮かんでくるのだ。そして妄想もしたくなる。じつに「想像力が刺激される本」なのである。
『絵のない絵本』でノヴァークの交響曲になった白鳥のモデルは?

チェコの作曲家であるノヴァークの交響曲『永遠のあこがれ(Eternal Longing)』は、この『絵のない絵本』第二十八夜の、海を渡る白鳥のお話から生まれた交響曲である。
この交響曲『永遠のあこがれ』を聴いていると、アンデルセンとノヴァークと自分に同じ映像が観えている感じさえする。『絵のない絵本』を執筆しているアンデルセンの頭の中にも、映画のように映像が浮かんでいたに違いない。
ヴィチェスラフ・ノヴァーク『永遠のあこがれ(Eternal Longing)』
『絵のない絵本』第二十八夜。越冬のため、空を飛んで移動する渡り鳥の群れ。いつしか遅れてひとり孤独に飛び続ける、力尽きそうな白鳥。「白鳥」「いたいけな姿」「醜いアヒル」…とくれば、この白鳥のモデルは、自分大好きアンデルセン!
ドイツでゲーテが詩人として活躍していた1800年代、デンマークの貧しい靴職人の家に生まれ、学校嫌いで空想壁のあるひきこもり少年だったアンデルセン。声楽家を目指して単身コペンハーゲンに上京するも、何者にもなれず失意と絶望を繰り返し、やがて哲学を学び旅に出て、旅を学校として旅ばかりの人生だったというアンデルセン。旅先で見たこと聞いたことをお話にして、『マッチ売りの少女』や『赤い靴』『親指姫』など160近い童話を生み出したアンデルセン。
『絵のない絵本』第二十八夜の白鳥は、瀕死ではあるけれど、ひどく傷つくことはない。何に襲われることもなく、無事に飛んでいく。自らを主役にしたお話だから、ひどい目には合わせられなかったのだろう。アンデルセンもノヴァークも、きっととっても「自分大好き」なロマンチストなのだ。
『絵のない絵本』第十六夜、哀しい恋の話を妄想してみた
同じく、『絵のない絵本』第十六夜に、道化師(プルチネッラ)の恋の話がある。この道化師は白鳥ではないので、アンデルセン自身が主役ではない。だから少し、悲しい目に合ってしまう。
背中と胸にコブのある
笑われ者役の道化師の男が
美しい女優に恋をする。
その女優は道化師が
自分を好きなことを知りつつ
男の友人と結婚し、
そして死んでしまう。
ある夜、男は女の墓でひとり泣く。
いい話である。けれど、男性が書いたせいか、なんだか甘い気がする。林真理子さんや中園ミホさんなら、この女優を、男の友人ではなくまずはこの道化師と結婚させるにちがいない。手加減することなく、妄想してみた。
道化師が恋した女は
道化師の親友に恋愛をしていた。(ここまで同じ)
でも女はついに振り向き、自分のものになる。
道化師は夢のような日々を送り、
幸せの絶頂を味わう。
でも女は突然に死んでしまう。
道化師は半狂乱になって道に飛び出し事故にあい、
女の墓に行くことさえ叶わない体になってしまう。
孤独な夜、動けない身体で
道化師はひとりベッドでむせび泣く。
お話なのだから、幸せにしてから突き落としたい。世界中で大ヒットした英国貴族一族のテレビドラマ『ダウントン・アビー』では、大悲劇の寸前にメアリーが出産し、夫婦と一族はこの上なく幸せな時間をかみしめる。そして、『ダウントン・アビー』としてはめずらしく、この幸せなシーンが長く描写されている。
禍福は糾える縄の如し。主役をひどい目に合わせるのは、作者の特権なのかもしれない。