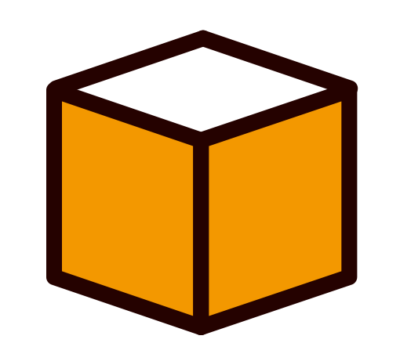介護施設の企画書でやってしまった失敗を振り返ってみた
企画書の書き方で検索している人は多いのではないだろうか。高齢者施設の企画に携わったことがある。介護施設は今や民間の運営が8割を超えているが、規制緩和により民間が参入し始めた頃で、老人ホームは建設ラッシュであった。
キレイにまとまった老人ホームの企画書、問題は何?
新しくオープンする有料老人ホームの案件で、提案項目に『各居室の名称、および居室前のプレートデザイン案』という項目があった。居室のプレートが数字だけでは、ビジネスホテルみたいで味気ない。毎日出入りする部屋だから、温かく演出したいし、高級感もにじませたい。『和風カラー辞典』を参考に、「桜」「山吹」「藤」「桃」「萌黄」などと各室に名前を付け、それぞれに綺麗なカラーチップを貼って企画書とプレートのラフデザインを仕上げた。締め切りに追われて早朝から深夜まで働いていたフリーランスのその当時は、つまり若くて元気だった。
その提案書は、今思い出しても恥ずかしい、浅はかな提案書だった。でもその「浅はかさ」に気づいたのは、それから何年も経った後のこと。入居者募集パンフレットの制作のために介護施設を取材した折だった。
「まずは取材を」と、関連する特別養護老人ホームやグループホームなども訪れることになった。新築でひと気のない、ピカピカの老人ホームを撮影で訪れたことはあったけれど、運営中かつ入居中のホームを訪問するのは初めての経験だった。
介護施設に「入りたくて」入る人は少ない
施設長さんによると、『老人ホーム』や『介護施設』という所に「入りたくて入る」ケースは、ほとんどない。他人には、できれば施設への入居は知られたくない。誰だって最期まで自分の家で暮らしたい。でも思うように動けなくなり、自力では日常生活が送れなくなって「自宅で暮らす」行為が限界になったため、折り合いをつけて「仕方なく入居する」、または「入れられる」場所でもあるという。「ここはもう私の家ではない」「もう私に家はない」と捉えている方が多いということだった。
介護の仕事は、恐れ入る仕事だった。 共用スペースで撮影中、杖をつきながら通りかかった高齢の女性が「その椅子、もとに戻してね」と怒ったようにいう。それも何度も。「はい、ちゃんと戻しますね」。このやりとりを、5分ほどの撮影のあいだに10回は繰り返しただろうか。認知症の人には、時間軸がないのだ。同じことを何度も言われたら、ただ同じことを返すだけでいい、ということを発見した。
「認知症」が入居条件のグループホームでは、めげない・明るい・たくましい、三拍子揃った女性スタッフが保育園の先生みたいなテンションで入居者に接していた。若いスタッフと談笑していた男性が突然に怒鳴りだし、突然に普通に戻った。まるで何もなかったように。突然に激高するタイプの認知症で、脳の問題なので怒っていることに理由はないということだった。自分が激高して怒鳴ったことも覚えていない、という。
老いるということ、人の身体はいつか壊れていくもの
老いるということは、大変なことなのだ。自分の2倍から3倍以上の時間を生きてきた人たちの姿に、老いを自分ごととして考えたことはなかったけれど、でも生きている限り必ず老いはやってくる。 精神や魂は変わらなくても、人の身体はだんだん壊れていくもので、頭も壊れていくものなのだ。そして自分の身体を持て余す日は、いつの日か誰もにやってくる。
老いをわが身に引き受けることが特に困難なのは、私達が常に、それを自分とは関係のない異質なものとみなしてきたからなのだ
哲学者 シモーヌ・ド・ボーヴォワール(Simone de Beauvoir)
私は依然として私自身であるのに、別の者となってしまったということがありうるの?
どの介護施設でも目についたのは、人の輪から離れるように一人で過ごす人の姿だった。庭で空を見たり、窓から外を見たり。何をするでもなく、ただ一人で座っている。
老人ホームでは、ベッドを出れば、自分一人で過ごせる空間はそうない。自分の居場所がないのに「家族のように快適に過ごせます」なんて、なんて薄っぺらい広告コピーなのだろう。当たり前だと思っていたけれど「自分の家で暮らせる」ということは、どれほど幸せなことなのだろう。
老人ホームの屋上には小さな庭園があり、濃いピンクのバラや紫のポインセチア、真っ赤なチューリップ等がまばらに植わっていた。高齢になるにつれ、眼は「藤色」「桜色」「水色」などの薄いトーンの色味が識別できなくなり、いずれも同じ「明るいグレー」にしか見えない、という。
フラッシュバックするように、20代の過去に手がけた企画書がよみがえった。そして、ある入居者の言葉が、 鋭く光った刃物のように心に突き刺ささった。
この介護施設は集合ポストが
201とか、305とかの部屋番号でよかった住所に施設の名前を書かなくても
この番号だけで私宛ての郵便が届くから
老人ホームに入ったことは言わずに
友達には引っ越ししましたって
住所と部屋番号だけ知らせてきたのよ
人には「自分だけの住所」が必要
年の暮れにニュース番組で、不況のあおりで路上生活をしていた男性がインタビューを受けていて、一番つらかったことは「年賀状がこなかったこと」と答えていた。「自分にはもう住所はないんだ、それを実感した、こたえた」と。
人にはいつまでも、老人ホームや介護施設に入っても、サクラやアオイやモエギやスミレではない、「〇丁目〇番地、〇号室」という住所が、「自分だけの番号」が必要なのだ。旅先のホテルや旅館の、 日常を忘れたい部屋と「自分の居室」は別のものだった。自分の住所とは、誇りや尊厳でもあるのだ。
マーケティングの基本は「現場にいって取材すること」
請負制作者に、施設に自ら足を運んで見たり、入居者にヒアリングをしたりする機会はあまりない。「入居者ファースト」「安心とやすらぎ」なんてコピーは、パソコンに向かって流れ作業で書かれたコピーである。企画をした…と錯覚しがちだけれど、ただの「思い込み」である。誰かの役に立つための企画なのに、誰に向かって、誰のために何を考えたつもりでいたのだろう?なんて浅い仕事をしていたんだろう?
やはり「現場へ行って取材をする」ことは、マーケティングの基本の基本だと思い至った。それ以来、介護施設や老人ホームの案件に関わることはないけれど、「自分の眼で見て」「ヒアリングする」ことの大切さが染みた経験だった。
有料老人ホームの取材で意外だったのは、初めて試食したペースト状の介護食のおいしさだった。管理栄養士といつも喧嘩しているという料理長の、味覚という「舌の喜び」を、最後の喜びを楽しんでほしい、という気持ちが込められている味わいだった。けれど介護施設には、自分が入るのも、家族や両親が入るのもできれば避けたい。鍼灸整骨院の院長が「若さは努力だ」「何もしないで若いはない」とおっしゃっていたが、寿命がやってくるその日まで元気でいられるように、身体が壊れてしまわないように、日頃からメンテナンスをして健康ファーストで暮らすことを「アンチエイジング」というのかもしれない。
若年は力を競うため、壮年は戦いに耐えられるため、老年は老苦に耐えるため。その身体を「健康」という。
「健康」とは思うように身体を使えることをいい、健康のためにいろいろ控えて動かない状態を「不健康」という。
哲学者 アリストテレス (Aristotelēs)