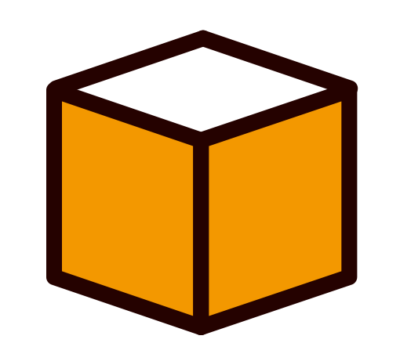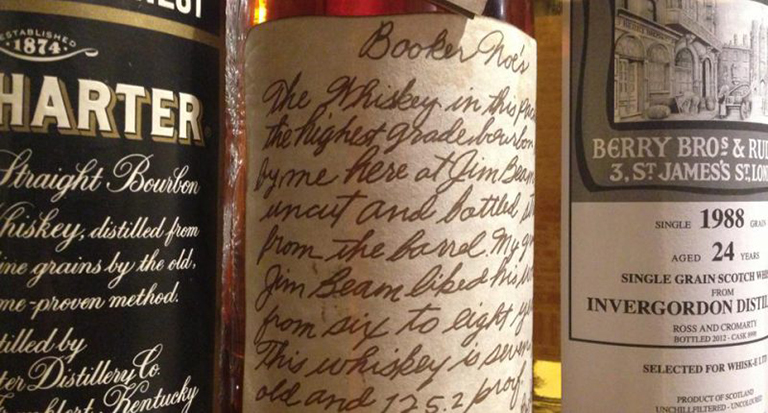バーを舞台にした短編小説|「特別なハイボール」|ショートショート
今夜も私がこの日一番の口開け客だった。映画好きのマスターから、最近の作品についてひとくさり話を聞きつつ一杯目を飲み干すと、矢来カットの8オンスタンブラーを静かにコースターに戻した。クラシカルなネジ巻式の柱時計を見て、「今日は少し遅いな」と思いながら次の一杯をオーダーしようとしたとき、静かにドアが開いた。
「いらっしゃいませ」
マスターの声にドアの方を見やったが、残念ながら期待していた顔ではなく、ソツなくスーツを着こなした30代半ばとおぼしき会社員ふうの男だった。
彼は、マスターに「どうも」と声をかけ、私の3つ隣の椅子を引いた。腰掛ける際、私に軽く目礼をくれ、私も応えた。たわいもない仕草だが、同じ空間を共有するのに欠いてはならない儀礼である。
「今日はお一人ですか?」
「いつもうるさくしてすみません」
マスターとの会話から、彼もこの店によく来る客だと察した。この店は、時間帯によって客層がまったく違う。だいたい早い時間は一人客ばかりが集うサロンとなるが、遅い時間になると2軒目や3軒目といった騒がしい酔客が連れもってやって来る。だから、同じ店の馴染み客だと言っても、お互いに面識はなかった。
「予定していた飲み会が流れて……」
彼は、咎められているわけでもないのにイレギュラーな来店を弁明した。
「いつもので?」
「そうですねぇ……」
彼がボトル棚を見ながらオーダーを考えているところ、再びドアが開いた。
「いらっしゃいませ」
来た。マドンナだ。
彼女の常連歴は私より古く、店では「ナオミさん」と呼ばれている。それが本名かどうかは知らないし、誰もそんなことは気にしてない。見たところ30代前半だが、はっきりとした年齢も知らない。ただ、未婚で独身だということだけは聞いていた。
彼女の服装はいつも大人しめで、ベージュや茶系が基調でメイクもナチュラル系。言葉使いや所作も美しく、およそ上品な育ちをしたのだろうと想像させられる。今日もシックなジャケットを、自分に似合うよう上手に着こなしていた。この店はむさい男どもが集うバーだが、彼女が現れると「掃き溜めに鶴」のごとくにわかに華やかになる。
※ ※
だいたいどこのバーにも女性の常連客が何人かいる。たいてい一人飲みを好み、女同士でおしゃべりを楽しむというタイプは少ない。そもそもバーはダンディズムの世界。男の社交場なので、女性は居るだけで目を引く。そこへ臆せず一人でやってくる女性は、一見か弱いレディーに見えても肝の座り方が違う。
ただし、バーの一人飲みの女性客なら、誰でもマドンナになれるとは限らない。それなりの容姿はもちろんのこと、立ち居振る舞いがエレガントで会話もウイットに富んでいなければならない。さらに、酒場の客である限り酒に強いのは必須条件だ。それも、酔って乱れるようなこともなく、いつでも誰にでも慈愛をもって接する聖母のようでなければマドンナにはなり得ない。だからこそ「ナオミさん」はこの店のマドンナであり、常連男たちのあこがれの君であるのだ。
※ ※
「こんばんわ」
彼女は私とマスターに目で挨拶を交わしたあと、コツコツとヒールの音を立て軽やかな足取りでカウンター端の定席へと向かった。そして、まるで晩餐会のテーブルに着席するかのように、新顔の客に穏やかな笑みを送りながら腰掛けた。
彼も薄く笑みを見せながら目礼を返したが、その刹那、まさかこんな男臭い酒場に麗しい妙齢な女性に出会うとは思わなかった、というような表情を見せた。おそらく彼は、同じ店の馴染み客なのに彼女の存在を知らなかったことに小さなショックを受けただろう。
「お決まりですか?」
マスターが「とにかく一杯やってから」とでも言いたげに、彼に注文を促した。彼はすぐさま平静を取り戻し、私と彼女を交互に手の平で指し示しながら「いつもは何を?」と尋ねた。会話のキッカケを作るために私と彼女に尋ねたのだろうが、もちろん、私ではなく彼女とのキッカケを得たかったに違いない。
私は氷だけになったタンブラーを手に「ハイボール」と答えると、彼女も「私もハイボール」と「も」のところをやや強調し、はにかむように微笑んだ。
「じゃぁ僕も彼女と同じので」
「彼女と同じものでいいですか?」
彼はオーダーを聞き返されたことがやや不満な感じで「えぇ」応えたが、私はマスターをフォローするために「こっちは普通のハイボールで」と付け加えた。彼は三人に疑問の顔を向けたが、マスターは「まずはお試しを」とばかりに含みのある笑顔を見せた。
「マドンナのハイボール」は強烈だ。普通、ウイスキーをソーダで割るのをハイボールと呼ぶが、彼女のスペシャルドリンクはウイスキーをビールで割る。これは、ボイラーメーカーと呼ばれるカクテルで、手早くガツンと酔いたい猛者のカクテルとして知られている。しかも彼女のレシピはウイスキーの割合が多く、この店では彼女以外に誰も飲まない。
だいたいどこのバーでも、マドンナと呼ばれる女性はウワバミ級なのが常である。ナオミさんも例外ではない。だからマドンナを「落とそう」などと考えて、同じように付き合うとエライ目に遭うことになる。
やがて常連たちがポツポツと集い、いつものように席を埋めた。今夜もマドンナは男たちと和やかにグラスを交え、そしてナイトたちに守られた。
案の定、「落ちた」のは彼の方だった。
以来、彼と私は、連日、口開け客の座を争っている。
(了)